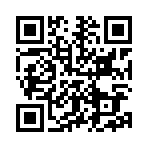2017年01月11日
《謹賀新年・炭のパワーは永遠です・やればできる》
◆謹賀新年、珍しく初日の出を見逃す。起床後20分ばかり散歩、朝風呂に入り、信子、金次郎と年の初めの挨拶・屠蘇を交わしおせちで朝食。少し遅れて健太郎・史恵・凜太郎・万次郎が加わり賑やかに、その後健太郎親子は史恵の実家に挨拶に。暮れに実父を亡くし嫁のお母さんも、嫁も慌ただしい毎日を過ごし疲労困憊、ゆっくり休んで欲しい。私は12時から田町顔合わせ・駅前だるま市・墓参と移動し早めに帰宅。だるま市は鐘や太鼓・三味で人集めは成功?だが、正月らしさは今一つ感じられなかった。
◆さて私の今年の目標は1まずは健康 2体重は72㎏以下 3リハビリ週2回 4早寝早起き 5即行即止 6素直 7整理整頓 8無償奉仕 9挨拶 10時間厳守 の10項目。あまり気張らずに呑気に実行を目指そう。やっとこ、体調も回復してきた。普段は仕事に励み、少しは自由な時間を楽しめるよう頑張ってみたい。1月22日ー26日ベトナム初めてのダラットに2月11日―15日3年ぶり中国湖南省へ出かける。現地での植林作業はまだ無理だが状況確認・企画・親睦程度なら問題なしであろう。
◆暮れに届いた幾つかの会報に、心揺さぶれる文が目についた。まずは「くまもり通信」川嵜實支部長の「故宮下正次顧問への追悼 炭の力を信じて」。宮下氏のご高説を聞いた川嵜氏は、10数年で深く宮下理論の実践をして各地の松枯れを防いだ。宮下顧問の研究指導に感謝しご冥福を祈る、と同時に川嵜氏の益々の活躍を期待したい。次は「さばく53号」。日本沙漠緑化実践協会の機関誌は近年、内容がより充実の感あり。発足当時の思い出から若い人の真剣に緑化に取り組む姿勢に感銘を受ける。少しく私の緑化活動の原点となる沙漠談義を。
◆遠山征瑛先生の「第1次中国沙漠開発日本協力隊」91年7月「広田住宅センター」の社員、平松義晴・後閑靖代さんも動員8次隊迄参加したが、1年強で遠山の親父と意見相違が生じ、我々は「地球緑化センター」を設立「実践協会」と袂を分かつ。暫くは疎遠であったがなんと「倫理法人会」で「実践協会」と接触、懐かしさのあまり2度訪問。そんな訳で中国通いは延々と続き内モンゴル沙漠、重慶の揚子江、承徳市の豊寧などへ私は都合40回強、訪中したが、ここ3年は病気と中国の強い姿勢?で凍結。
◆その「日本沙漠緑化実践協会」の会員も、植林活動の参加者も、寄付も減少、財政が厳しいと。更に世界の経済大国になった意地悪中国になんで我々が植林の手伝い、オカシクナイ?との声が、多いのも確か。でも一度でも沙漠で穴を掘り、木を植えた人はその時点で、その木が育って欲しいと素直に願っていると思う。どこに線が引いてあるのか、同じ地球だ。また、植林現場で村人や中国学生達と一緒に作業をし、心を通じ合えた感想は、皆良い人ばかり。そんな文面から私は思い、祈る。若い人達の心に≪地球は一つ≫が根付かないかな、と。
◆久し振りの訪中に今、わくわくしている。蒋家村は4回目、蒋雄軍さんは村の人達のカンパで日本留学・高崎経済大学で大宮登ゼミに所属。在学中から『日中友好桜プロジェクト』の私案を先生に相談、彼の熱意が先生を、周囲を動かし10年間の活動となった。今や禿山は緑に覆われ、果実も沢山収穫でき、小動物も棲息し、計画的農業に励み、生活も大分余裕が出てきた様子。大宮先生の物心にわたる強力な支援がおおきな成果をもたらした。素晴らしい≪故郷に錦を飾る≫≪師弟愛・日中交流編≫物語はまだまだ続く、そして第2ステージに。
◆今年は暖かな正月でスタートでき、良かったですね。私も倒れてから2年強、何とか周囲の手助けで仕事にも復帰でき、今、自分は幸せなのだと思う。取り敢えず、後遺症もなく、無理はできぬが普通の生活を楽しめる。あと何年持つかわからぬが、きっと逝く時は一発で逝き、妻子に手を煩わせぬであろう。大体、死に方もわかってきた。さあ、あとは13年間でしっかりと終活整理してゆけばよい。年頭においてゆっくりとこれからの『生き方』と『終い方』を考えることが出来た。感謝しまーす。
2017年1月1日 広田誠四郎 記
◆さて私の今年の目標は1まずは健康 2体重は72㎏以下 3リハビリ週2回 4早寝早起き 5即行即止 6素直 7整理整頓 8無償奉仕 9挨拶 10時間厳守 の10項目。あまり気張らずに呑気に実行を目指そう。やっとこ、体調も回復してきた。普段は仕事に励み、少しは自由な時間を楽しめるよう頑張ってみたい。1月22日ー26日ベトナム初めてのダラットに2月11日―15日3年ぶり中国湖南省へ出かける。現地での植林作業はまだ無理だが状況確認・企画・親睦程度なら問題なしであろう。
◆暮れに届いた幾つかの会報に、心揺さぶれる文が目についた。まずは「くまもり通信」川嵜實支部長の「故宮下正次顧問への追悼 炭の力を信じて」。宮下氏のご高説を聞いた川嵜氏は、10数年で深く宮下理論の実践をして各地の松枯れを防いだ。宮下顧問の研究指導に感謝しご冥福を祈る、と同時に川嵜氏の益々の活躍を期待したい。次は「さばく53号」。日本沙漠緑化実践協会の機関誌は近年、内容がより充実の感あり。発足当時の思い出から若い人の真剣に緑化に取り組む姿勢に感銘を受ける。少しく私の緑化活動の原点となる沙漠談義を。
◆遠山征瑛先生の「第1次中国沙漠開発日本協力隊」91年7月「広田住宅センター」の社員、平松義晴・後閑靖代さんも動員8次隊迄参加したが、1年強で遠山の親父と意見相違が生じ、我々は「地球緑化センター」を設立「実践協会」と袂を分かつ。暫くは疎遠であったがなんと「倫理法人会」で「実践協会」と接触、懐かしさのあまり2度訪問。そんな訳で中国通いは延々と続き内モンゴル沙漠、重慶の揚子江、承徳市の豊寧などへ私は都合40回強、訪中したが、ここ3年は病気と中国の強い姿勢?で凍結。
◆その「日本沙漠緑化実践協会」の会員も、植林活動の参加者も、寄付も減少、財政が厳しいと。更に世界の経済大国になった意地悪中国になんで我々が植林の手伝い、オカシクナイ?との声が、多いのも確か。でも一度でも沙漠で穴を掘り、木を植えた人はその時点で、その木が育って欲しいと素直に願っていると思う。どこに線が引いてあるのか、同じ地球だ。また、植林現場で村人や中国学生達と一緒に作業をし、心を通じ合えた感想は、皆良い人ばかり。そんな文面から私は思い、祈る。若い人達の心に≪地球は一つ≫が根付かないかな、と。
◆久し振りの訪中に今、わくわくしている。蒋家村は4回目、蒋雄軍さんは村の人達のカンパで日本留学・高崎経済大学で大宮登ゼミに所属。在学中から『日中友好桜プロジェクト』の私案を先生に相談、彼の熱意が先生を、周囲を動かし10年間の活動となった。今や禿山は緑に覆われ、果実も沢山収穫でき、小動物も棲息し、計画的農業に励み、生活も大分余裕が出てきた様子。大宮先生の物心にわたる強力な支援がおおきな成果をもたらした。素晴らしい≪故郷に錦を飾る≫≪師弟愛・日中交流編≫物語はまだまだ続く、そして第2ステージに。
◆今年は暖かな正月でスタートでき、良かったですね。私も倒れてから2年強、何とか周囲の手助けで仕事にも復帰でき、今、自分は幸せなのだと思う。取り敢えず、後遺症もなく、無理はできぬが普通の生活を楽しめる。あと何年持つかわからぬが、きっと逝く時は一発で逝き、妻子に手を煩わせぬであろう。大体、死に方もわかってきた。さあ、あとは13年間でしっかりと終活整理してゆけばよい。年頭においてゆっくりとこれからの『生き方』と『終い方』を考えることが出来た。感謝しまーす。
2017年1月1日 広田誠四郎 記